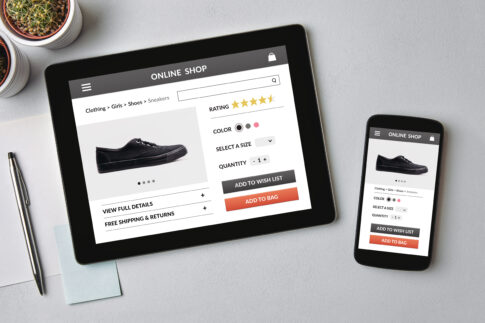ブランドリフトとは、広告やプロモーションによってブランドに対する認知や好感度、購買意欲がどれだけ変化したかを測る指標であり、広告接触前後で人々の意識や購買意欲がどう変化したかを数値化し、広告の効果を可視化するものです。
このような数値は自社アンケートやWebツールだけでは可視化が難しいため、数十万円から数百万円をかけて広告プラットフォームや調査会社に依頼し、調査をするのが一般的です。なぜなら、正確な数値を出すためには数千件のサンプル数や独自のノウハウ、計算式が必要となるからです。
この記事では、forUSERS株式会社でマーケティングを担当している筆者が、ブランドリフトについて解説します。
ブランドリフトを活用して「交通広告の効果」を測定した筆者の体験談
筆者が、かつて所属していた英会話スクールでは、首都圏の主要な電車内広告を中心に交通広告を展開していました。
調査会社に依頼をし、電車広告の印象や、クリエイティブを見た方の来校意欲について、広告接触者と非広告接触者に分けて定期的に調査を実施したところ、効果測定の中で、広告クリエイティブの内容によって「ブランドリフト」の数値に明確な差が出ることもありました。
そのため、広告クリエイティブの訴求(デザインやキャッチコピー)は、新規顧客の獲得に直結する重要な要素と社内で認識されており、広告クリエイティブを制作するエージェンシー選定においては、コンペ形式で広告クリエイティブをプレゼンしてもらい、最も反響が期待できるエージェンシーを選定しておりました。
その広告クリエイティブの効果測定として、ブランドリフトの数値を使うことで、前回とのクリエイティブ比較を行い、エージェンシーや広告クリエイティブを数字で評価していたのです。
このように、季節ごとに大きな予算を使ってクリエイティブを準備する大企業では、クリエイティブごとに効果や印象を比較するため、ブランドリフトを利用しております。
ブランドリフトの調査例
ブランドリフトにはさまざまな調査手法があり、計算式も複数あります。ここでは架空の調査をもとにブランドリフト調査の一つの計算式を紹介します。
※ここではブランドリフトを理解するために「カンタンな数値と計算式」でブランドリフトを紹介しております。
とある広告キャンペーンを「見た人」と「見ていない人」でグループを2つに分け、消費者の態度や意識が広告によってどれだけ変化したかを調査します。以下は、その計算式の例です。
◆ブランドリフトの計算方法の例
ここでは、以下のような数値であったとしましょう。
・広告を見ていない人のうち、肯定的な回答をした人の割合:40%
◆計算式の例
つまり、「広告によって、ブランドリフトが20%上昇した」という意味になり、広告によって、ユーザーが好意的になったり、購買意欲が高まったことが分かります。しかし、その他の外的要因(価格、流通、競合要因)に左右されることも多いため、あくまで参考的な数値としてとらえます。
ブランドリフトを調査する2つの方法
ブランドリフトを調査する方法としては、以下の2つの方法があります。
方法② 調査会社を利用する
それぞれの特徴を比較表にしてみました。
◆ブランドリフトの調査方法の比較表
| 比較項目 | 方法① 広告配信プラットフォーム | 方法② 調査会社 |
|---|---|---|
| 主なサービス提供元 | Google、YouTube、Metaなど | マクロミル、クロス・マーケティングなど |
| 調査の流れ | 広告配信と連動してツールで自動的に実施 | 調査設計〜実査・分析まで手動で実施 |
| 設計の自由度 | 限定的(媒体ごとに固定フォーマット) | 高い(質問項目・分析軸を柔軟に設定可能) |
| データの客観性 | プラットフォームのデータに依存 | 客観性が高い |
| スピード | 早い(即日〜数日で結果が出る) | 時間がかかる(1〜2週間程度) |
| 費用感 | 数百万円~ | 数十万円~ |
| 向いているケース | 広告効果を素早く確認したい場合 | 詳細な分析や報告用データが必要な場合 |
それでは一つずつ解説します。
方法① 広告配信プラットフォームを利用する
GoogleやYouTube、Meta(旧Facebook)などの広告配信プラットフォームでは、ブランドリフト調査を自社で実施できる機能が用意されています。たとえば、Google広告では「ブランドリフト調査」という機能を使うことで、広告に接触したユーザーと非接触ユーザーの認知度や想起率などを比較し、広告効果を測定することが可能です。例えば、Meta社でもブランドリフト調査について、以下のようにWebサイトで案内を出しております。
これらのプラットフォームでは、広告配信と調査設計が連動しており、ユーザーに自然な形でアンケートが表示されます。そのため、配信から調査までの一連の流れが自動で実施されるため、手間がかかりにくいのが特徴です。
ただし、各プラットフォームごとに調査設計の自由度や、測定できる項目に違いがあるため、目的に応じて最適な媒体を選定する必要があります。費用感は、プラットフォームごとに違いますが、数百万円~※と大手企業でなければ実施が難しい価格帯となっています。
方法② 調査会社を利用する
マクロミルやクロス・マーケティングなどの調査会社を活用する方法も、ブランドリフトを測定する手段の一つです。これらの調査会社では、ターゲット属性に合ったモニターを抽出し、広告接触者・非接触者に対してアンケートを実施することで、広告がブランド認知や購買意欲に与えた影響を数値化できます。
プラットフォーム内での調査と比べて、調査設計の自由度が高く、質問項目や分析軸を細かくカスタマイズできるのが強みです。また、第三者視点での客観的な調査が可能となるため、クライアントや社内向けの報告資料として説得力が高いデータを得られるのもメリットです。
一方で、調査設計から実査・分析までに一定の時間とコストがかかるため、スケジュールや予算に余裕を持って進める必要があります。調査会社大手のマクロミルでは下記に価格表が公開されているので、これからブランドリフトを実施する企業は参考に下記をご覧ください。
参考:料金表(マクロミル)
なお、このような調査会社は、大手エージェンシーが提供する広告クリエイティブの見積に入っていることが多く、大手エージェンシーの場合は、これらの調査も調査会社と協力して一環して実施するケースが多い印象です。
ブランドリフトを実施すべき企業とは?「ブランド認知」が目的である場合
ブランドリフト調査はすべての企業に必要というわけではありません。特に実施を検討すべきなのは、「ブランド認知」をマーケティングの主要目的としている企業です。
たとえば、新商品や新サービスをローンチしたばかりの企業、あるいは既存ブランドの再構築(リブランディング)を進めている企業にとっては、広告の影響がユーザーの認知や印象にどう反映されているかを把握することが非常に重要です。
また、マス広告や動画広告など、比較的リーチの広い施策に投資している企業にとっては、ブランドリフトの指標をもとにPDCAを回すことで、広告費の費用対効果をある程度評価することが可能になります。
一方、すぐに売上やコンバージョンを追いたい短期的なキャンペーンにおいては、ブランドリフトよりも直接的なパフォーマンス指標(CVRやCTR)の方が適していますので、このような場合は、ブランドリフトは適しておりません。
ブランドリフト調査の2つの注意点
ブランドリフト調査は広告の効果を可視化する上で非常に有効ですが、実施する際にはいくつかの注意点があります。
注意点① サンプル数に注意が必要
信頼できる統計データを得るためには、十分なサンプル数を確保する必要があります。特にセグメント別に分析を行いたい場合には、各層での回答数が少ないと誤差が大きくなり、判断を誤る可能性があります。
たとえばGoogleのブランドリフト調査では、1つの質問あたり、回答者が1,000人未満だと統計的なブレが大きくなり、信頼性のある差分が測定できない可能性があります。広告のインプレッション数やクリック数が十分にあっても、実際にアンケートに回答する人数が少なければ、調査全体が意味をなさないこともあるのです。
また、細かなセグメント(たとえば地域別・年代別など)で結果を比較したい場合、それぞれのセグメントでも十分なサンプル数が必要になりますが、セグメントを絞り過ぎるとサンプル数が集まらないことも多々あります。
そのため、事前に「どこまでの粒度で分析したいか」を明確にし、それに応じた配信設計・調査設計を行うことが重要です。
注意点② ブランドリフトのポジティブな変化が良いとは限らない!
ブランドリフトの数値が改善していても、実際の売上や中長期的なブランド価値につながっていないケースもあります。ブランドリフトの結果はあくまで「仮説のヒント」として活用し、以下の例のように他のKPIと併せて総合的に判断することが大切です。
◆飲料メーカーの例
ある飲料メーカーが新商品のテレビCMを放映し、調査の結果、「広告想起率」や「ブランド好意度」は大きく向上した。しかし、販売データを見ると、該当地域での売上はほとんど変化がなく、最終的に「価格設定が競合と比べて高かったこと」「販路が限られていたこと」がボトルネックだったと判明した。
このように、ブランドリフトの数値は「広告が心に残ったか?良い印象を与えたか?」といった心理変容を示す指標であって、購買行動を促す他の要因(価格・流通・競合動向など)との組み合わせで初めてマーケティング戦略が見えるのです。
この結果を受けて、「次回は価格訴求を強めたコピーで展開しよう」「販路の拡充も同時に進めよう」など、次の施策の仮説を立てる材料の一つとして、ブランドリフト調査を活用するべきなのです。
ブランドリフト調査は「効果測定」ではなく「仮説の出発点」
ブランドリフト調査は、広告によってユーザーの認知や好意度、購入意向がどのように変化したかを明らかにする手段として、多くの企業に活用されています。特に「広告の効果を感覚ではなく、データで判断したい」という場合に力を発揮します。
広告効果を可視化するためのブランドリフト調査は、決して万能ではありませんが、次の打ち手に生かせる一つの手法となります。重要なのは、調査結果をゴールと捉えるのではなく、次のマーケティング施策を考えるための「仮説の出発点」にすることでしょう。
もし、EC事業者において、これからマーケティング戦略をコンサルに依頼して行いたい場合は、インターファクトリーのEBISU GROWTH(エビス グロース)にご相談ください。EC経験の実績豊かなコンサルタントがお手伝いいたしますので、下記の公式サイトよりお申し込みください。